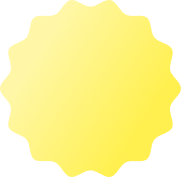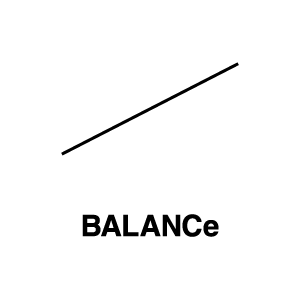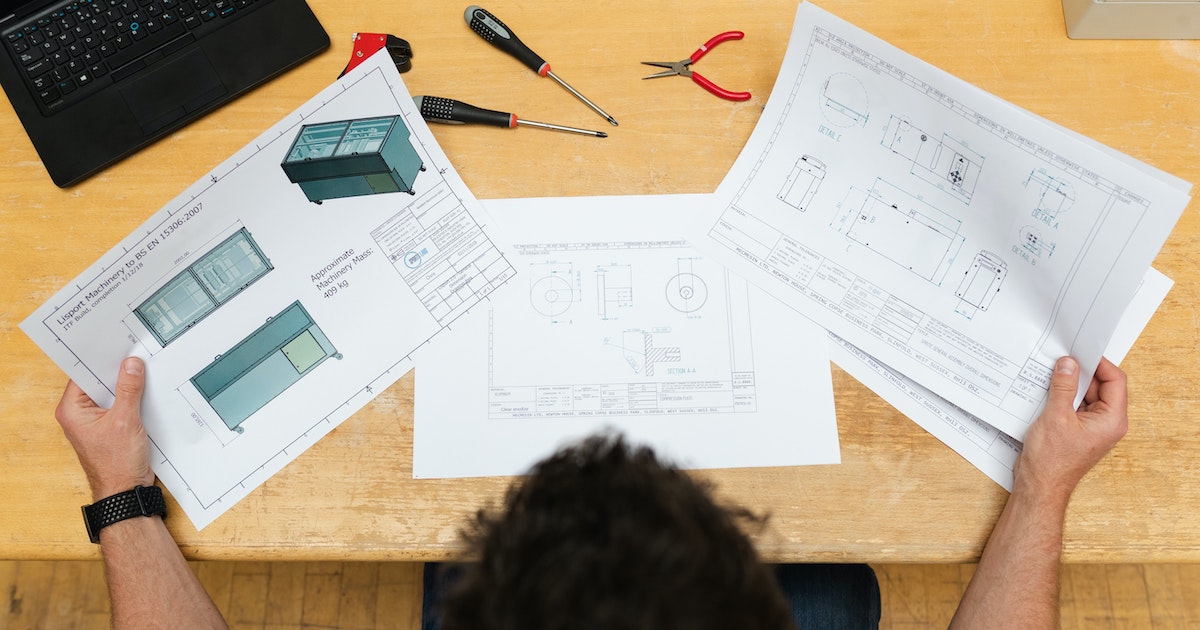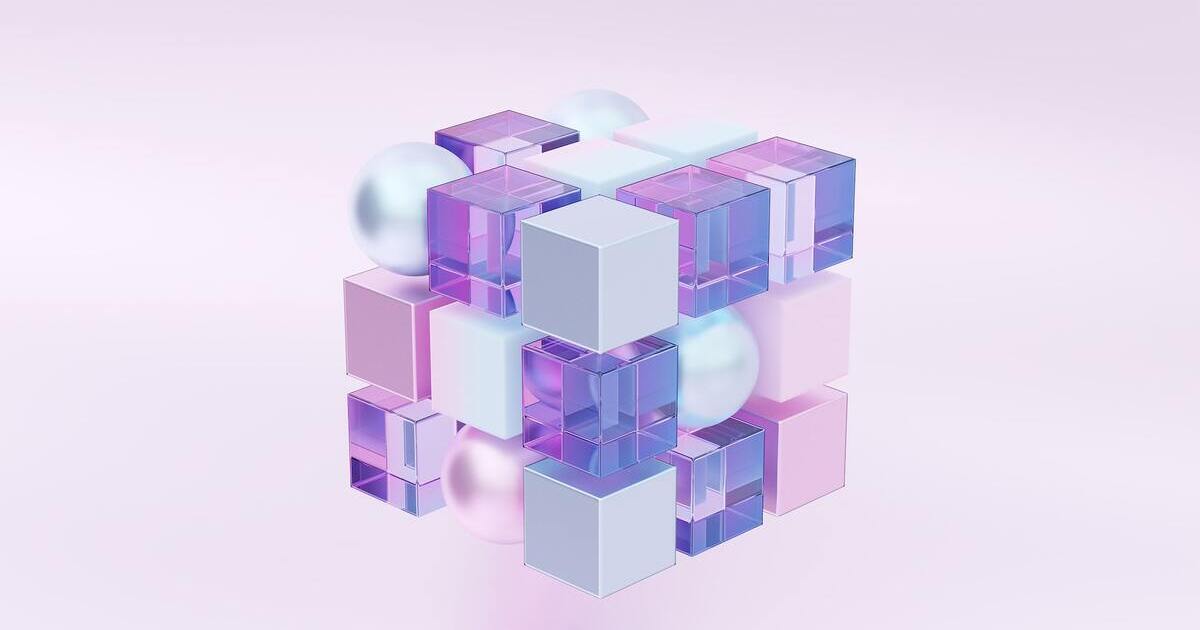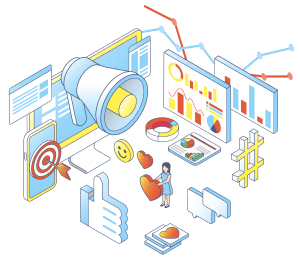ホームページ制作に活用できる補助金や手順・注意点などを解説!

ホームページ制作には、補助金を活用できる制度があります。ホームページ制作に補助金を活用したいと考えていても、企業の担当者の中には「どの補助金を使えるのか分からない」「申請手順が複雑で不安」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事ではホームページ制作に活用できる補助金の種類、申請の流れ、注意点について詳しく解説します。本記事を読めば、補助金活用の全体像を把握でき、制作依頼や申請準備に役立ちます。
弊社では、情報発信業務の効率化を実現するCMSや、パーソナライズされたマーケティングを実現するCRMの組み込み、ポータルサイト制作も対応可能!
メーカーや不動産企業の制作実績も多数。
ホームページ制作に活用できる補助金4選
中小企業や小規模事業者はホームページ制作に補助金を活用でき、費用負担を大幅に軽減できます。国は、中小企業のデジタル化推進のため制作費用の一部を補助する制度を設けています。
例えば、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、中小企業新事業進出補助金の4つが、ホームページ制作に活用可能です。補助金制度を活用すれば、初期投資のハードルを下げつつ効果的な自社サイトを構築できるでしょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業がITツールを導入する際に活用できる代表的な補助金制度です。労働生産性の向上や業務効率化を目的に、ソフトウェアやサービス等の購入費用の一部を国が補助します。
また、ホームページ制作など幅広いIT活用が補助対象で、毎年多くの企業が業務効率化や販路拡大で着実に成果を上げているのです。コスト負担を減らしながらデジタル化を進めるため、中小企業にとって心強い支援策となっています。
IT導入補助金の対象者
IT導入補助金の対象者は、日本国内で事業を営む中小企業・小規模事業者(法人・個人事業主)です。業種は製造業から飲食業・サービス業まで幅広く、資本金や従業員数が一定以下であれば対象です。
小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下、製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下と定められています。ほとんどの中小企業がこの条件を満たすため、幅広い企業が申請可能です。
IT導入補助金の対象ツール・要件
IT導入補助金で導入できるITツールは、事務局が事前審査し公式サイトに公開したソフトウェアやクラウドサービス等に限られ、申請時はその中から選定する必要があります。中小企業側は、ITツール提供事業者と連携して申請を行う仕組みです。
ITツール自体にもいくつか要件があり、業務効率化や売上向上に資する機能を持つことが条件です。顧客管理や販売支援、会計などの業務プロセスを1つ以上含むITツールである必要があり、汎用的なツール単体では認められません。
補助対象経費にはソフトウェア購入費やクラウド利用料のほか、導入設定やコンサルティング等のサービス費用も含まれます。
IT導入補助金の補助率や上限額
IT導入補助金の補助率は、原則として導入費用の1/2ですが、一定条件を満たす場合は2/3に引き上げられます(賃上げの実施など)。
補助金額の上限は導入内容によって異なります。1~3つのプロセスに留まるIT導入の場合は上限150万円、4つ以上のプロセスを含む大規模導入の場合は上限450万円に設定されるのです。
また、賃上げなどの条件を達成した企業では補助率2/3が適用され、自己負担がさらに軽減されます。最低補助額は5万円で、これに満たない小規模な導入は対象外です。
このように、数十万~数百万円規模のIT投資に対し手厚い補助が得られるため、中小企業のIT導入における費用負担軽減に大きくつながっています。
IT導入補助金の申請スケジュール
IT導入補助金の公募は例年複数回行われ、年度内にいくつかの申請期間が設けられます。
2024年度は通年で計4回の公募が実施され、おおむね春から秋にかけて順次締切と採択結果の公表が行われました。2025年度も3月末に募集開始し、第1回締切は5月中旬、以降も秋頃まで複数の締切日が予定されています。
最新の公募スケジュールは公式サイトで公開されているため、申請を検討する際は必ず事前に確認が必要です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営計画に基づいて販路開拓や業務効率化に取り組む際に、その費用の一部を国が補助する制度です。
新たな顧客を開拓するためのホームページ制作費用など、販路拡大に必要な経費を支援し、経営の持続的発展を後押しします。資金や人手が限られる小規模事業者にとって、この補助は販路開拓の費用負担を軽減し、成長機会に積極的に取り組みやすくするメリットがあります。
小規模事業者持続化補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象となるのは、商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者(特定非営利活動法人(NPO法人)を含む)です。
具体的には、従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業その他で20人以下の会社や個人事業主など、小規模企業の定義に該当する事業者が含まれます。
日々の経営において資源が限られる小さな事業者ほど、販路開拓や新たな取組へのハードルが高いため、こうした企業を支援するのが本制度の目的です。
小規模事業者持続化補助金の補助率や上限額
補助率は原則2/3(赤字事業者の場合は一部3/4)で、基本的な補助上限額は50万円です。ただし、要件に応じて上限額が引き上げられる特例が用意されています。
事業内最低賃金を地域の最低賃金より30円以上高くするなど賃金引上げの取組を行う場合には「賃金引上げ枠」として上限が200万円に拡大されます。また、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応要件を満たす事業者には、補助上限額にさらに50万円が加算されるのです。
さらに、販路開拓の内容に応じて「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠も設けられており、いずれも通常枠より補助上限額が高く最大200万円まで支援が受けられます。
小規模事業者持続化補助金の申請スケジュール
小規模事業者持続化補助金は年に複数回の公募が行われています。直近では第16回公募が2024年5月27日に締め切られ、同年8月8日に採択結果が発表されました。
2025年春には第17回公募も行われ、申請締切は同年6月中旬頃に設定されています。
基本的に数ヶ月おきに公募が実施され、申請締切からおよそ2~3ヶ月後に採択結果が公表されるスケジュールです。今後の募集予定については公式サイト上で随時案内されます。
新事業進出補助金
2025年度から開始された新事業進出補助金は、中小企業が既存事業とは異なる新たな市場や高付加価値分野に事業を拡大する際の設備投資などを支援する制度です。
新しい事業への積極的な挑戦を促すために、機械装置の導入や施設整備などの大きな初期投資に対して国が補助金で支援します。
新事業進出補助金によって、中小企業がリスクを抑えつつ新規事業に踏み出し、事業規模の拡大や付加価値向上を図ることが期待されています。
新事業進出補助金の対象者
本補助金の対象者は、新規事業への挑戦を行う中小企業(中堅企業や個人事業主を含む)です。
中小企業基本法で定義される中小企業に該当し、資本金や従業員規模が一定以下であることが要件となります。既存事業とは異なる事業分野にて成長・拡大を目指す企業であることが求められ、付加価値額の向上や賃金引上げなど、将来的な発展に向けた計画を有する事業者が対象です。
業種や地域を問わず、全国の中小企業が広く対象となっています。
新事業進出補助金の補助率や上限額
補助率は補助対象経費の1/2(企業が残り半分を負担)で、企業規模(従業員数)に応じて補助金の上限額が設定されています。
- 従業員数20人以下:上限2,500万円(特例時3,000万円)
- 従業員数21~50人:4,000万円(同5,000万円)
- 従業員数51~100人:5,500万円(同7,000万円)
- 従業員数101人以上:7,000万円(同9,000万円)
補助下限額は750万円で、それ未満の事業規模では申請できません。
さらに、事業終了時に一定の賃上げ目標を達成した場合は補助上限が特例枠として拡大され(上記カッコ内の金額)、意欲的な企業ほど手厚い支援が受けられる仕組みです。
新事業進出補助金の申請スケジュール
新事業進出補助金は2025年度に創設され、第1回公募が6月17日に開始されました。申請受付に先立ち、4月22日に公募要領が公開されています。初回の申請締切は2025年7月10日18時までと設定されており、2025年6月現在、審査中です。
採択結果の公表は通常、締切から数ヶ月後になる見込みですが、正式な日程は決まり次第発表されます。第2回以降の公募予定を含め、今後の情報は公式サイトで順次案内される見込みです。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げを目的に、新製品・新サービス開発に必要な設備投資などを支援します。
公募ごとに審査が行われ、採択率は例年30〜50%です。補助対象経費は機械装置・システム構築費、専門家経費、外注費など様々です。補助枠には「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」が設けられています。「製品・サービス高付加価値化枠」は新製品・サービスの開発による高付加価値化を、「グローバル枠」は海外展開による国内生産性向上を目的としているのです。
これらの枠では広告宣伝費や販売促進費も補助対象経費に含まれます。新事業の販路開拓手段としてホームページを新規制作する場合、その制作費も補助対象となります。
ただし、広告のみを目的とする取組や、既存ホームページのリニューアルは補助対象外です。
補助金を活用したシステム開発についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
ものづくり補助金の対象者
ものづくり補助金の対象者は、中小企業・小規模事業者等です(製造業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下など)。応募にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
- 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率が+3.0%以上であること
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が直近5年間の地域別最低賃金の年平均上昇率以上、または年平均+2.0%以上であること
- 事業所内最低賃金が地域最低賃金+30円以上であること
- 従業員数21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
これらの数値目標は、生産性の向上と賃上げを促すために設定されています。補助事業終了後3〜5年の事業計画期間内に達成する必要があるのです。
従業員がいない個人事業主でも申請可能で、その場合は役員報酬の引上げ等により上記の給与要件を満たす必要があります。
ものづくり補助金の補助率や上限額
補助率は原則、中小企業で1/2(小規模事業者や再生事業者等は2/3)です。補助上限額は枠により異なります。製品・サービス高付加価値化枠では、従業員数に応じて上限額が750万円(5人以下)〜2500万円(51人以上)となります(賃上げ特例適用時は最大3500万円)。
グローバル枠では従業員数を問わず一律3000万円(特例時4000万円)です。上限額は条件次第で最大4000万円までの支援が受けられます。
ものづくり補助金の申請スケジュール
2025年度は、複数回の公募が予定されています。第19次公募は2月14日に開始し、申請締切は同年4月25日17時でした。第20次公募は4月25日に開始され、締切は7月25日17時です(採択結果は10月下旬予定)。
今後も年内に第21次以降の公募が行われる見込みです。概ね四半期に1度のペースで公募が行われており、年間3〜4回の募集締切があります。最新の公募スケジュールは公式サイトで随時確認できます。
弊社ではマーケティングの知見を用いた成果に繋がりやすいホームページの制作を得意としています。弊社でのWeb制作事例やサービス概要についてはこちらからご確認ください。
BALANCeのサービス
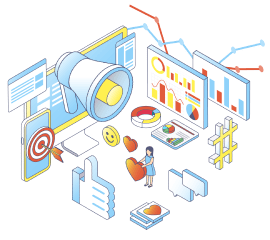
ブランディング、リード獲得のためのWebサイトを制作いたします。
マーケティング上の数値向上を最優先に、機能性とデザイン性が両立した制作・開発を行います。
【地方自治体・団体別】ホームページ制作に活用できる補助金
国だけでなく、地方自治体や団体でも中小企業向けにホームページ制作費用を補助する制度が充実しています。主な例として、次のような制度があります。
- 東京都江東区:ホームページ作成費補助-補助率1/2、上限10万円(初めてサイト開設時が対象)
- 東京都中央区:ホームページ作成費補助金-補助率1/2、上限30万円(新規作成・既存サイト改修が対象)
- 東京都港区:創業・スタートアップ支援事業補助金-補助率2/3、上限30万円(創業2年以内の中小企業、ホームページ新設時が対象)
- 大阪府吹田市:中小企業ホームページ等作成事業補助金補助率1/2、上限20万円(市に登録されている事業者へのホームページ制作・改修依頼が対象)
- 愛知県:あいちDX推進補助金-ホームページ制作を含むデジタル化への支援で補助率1/2〜2/3、上限100万円
このように、多くの自治体で、ホームページ制作に活用できる補助金が設けられています。
東京都でおすすめのホームページ制作会社についてはこちらで解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
ホームページ制作に補助金を活用するメリット
補助金を活用してホームページを制作・改修すると、次のようなメリットがあります。
| メリット | 効果 |
| 費用負担の軽減 | 補助金により制作費用の一部が賄われ、自社の負担が減る |
| 他予算への資金転用 | 浮いた資金を他の事業投資やマーケティングに回せる |
| 高機能サイトへのリニューアル | 補助を受けることで予算に余裕が生まれ、高品質なデザインや機能を導入したホームページに刷新できる |
| 専門業者への依頼のしやすさ | 費用補助があることでプロの制作会社に委託しやすくなり、より完成度の高いサイトを構築できる |
| 集客や信頼性の向上 | 助成により実現した充実したホームページは、顧客からの集客力や企業の信頼性向上につながる |
このように、補助金の活用はコスト面の不安を軽減し、企業のWeb戦略をより強力に後押しします。
弊社ではホームページの企画・制作・運用など、幅広くご提案が可能です。「補助金を活用したホームページ制作」。ご相談と提案は無料となりますので、補助金の活用を検討している方はぜひこちらからお問い合わせください。
弊社では最新テクノロジーを活用したサイト制作も対応可能!
お見積もりやご提案はもちろん無料です。ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。
ホームページ制作に活用できる補助金を受給するまでの手順
ホームページ制作で補助金を活用する手順は、大きく5つのステップに分けられます。事前準備から受給まで各段階での手続きが必要です。
まず申請書類を揃えて公募期間内に申請し、採択後に事業を実施・報告します。適切な報告と請求を経て補助金が支払われ、その後の効果報告までが一連の流れです。
以下で詳しく解説します。
1.申請に必要な書類を準備する
補助金を申請するには、公募要領を確認し、必要書類を正確に揃えます。
一般的に、申請書や事業計画書、直近の確定申告書類(決算書類)、法人の場合は履歴事項全部証明書や定款コピー、個人事業主の場合は開業届や本人確認書類などが求められます。
事業計画書は採択可否を左右する重要書類で、補助金の目的に沿った説得力のある内容を作成する必要があるのです。
補助金の種類によっては、IT導入補助金でのIT導入支援事業者への相談や、小規模事業者持続化補助金で商工会・商工会議所による支援計画書の作成依頼が必要となる場合もあります。
また、書類の不備は不採択につながるため、提出前に確認しましょう。
2.公募期間内に申請手続きを行う
補助金ごとに公募期間(申請受付期間)が設定されており、期限内に必ず申請手続きを完了する必要があります。期限を過ぎると申請は受け付けられません。
現在ではほとんどの補助金が電子申請(オンライン申請)で行われ、政府の補助金ポータル「Jグランツ」経由で申請手続きを行います。一部の補助金では申請に「GビズIDプライムアカウント」が必要となり、アカウントの取得に2〜3週間程度かかるため事前準備が重要です。
3.採択後に事業を実施・報告する
採択されたら、補助対象のホームページ制作事業を所定の期間内に実施します。事業完了後は速やかに実績報告を行い、契約書や請求書、納品書、支払証明など必要な証憑書類をすべて添えて提出します。
実績報告書の提出期限は補助事業完了日から30日以内など各補助金で定められており、期限厳守が大切です。
IT導入補助金や事業再構築補助金、ものづくり補助金などでは、補助事業完了後にこれらの報告義務があり、報告内容の審査(確定検査)を経て補助金額が確定します。
ものづくり補助金では、事業完了後も毎年度「事業化状況報告」を提出する必要があり、採択から5年間にわたり計6回の報告が義務付けられています。
4.補助金を受け取る
実績報告の内容が認められると、補助金額が正式に確定します。その後、補助金事務局に補助金の請求手続きを行い、問題がなければ指定した口座に補助金が振り込まれます。
補助金の振込までは請求手続き完了後から約1ヶ月を要するケースが一般的です。補助金が入金されれば、補助事業の全工程が完了します。
補助金によっては設備の現地検査などが実施される場合もあるのです。現地確認では、導入設備の設置状況などを検査します。
5.実施効果を報告する
補助金受領後も、事業の効果や経営への影響を報告する義務が課されています。IT導入補助金では導入後に年次の効果報告を3〜4年間行う必要があるのです。
小規模事業者持続化補助金では、事業完了から約1年後に売上高等の事業成果を報告します。また、事業再構築補助金では、事業完了後は最大5年間、毎年事業化状況報告(効果報告)を行う必要があるのです。
ものづくり補助金では、実績報告の提出期限が補助事業完了後の翌月15日までとされており、その後5年間は毎年度の事業化状況報告が課されます。
補助金を活用したホームページ制作は株式会社BALANCeがおすすめ

補助金を活用したホームページ制作では、制作経験が豊富で補助金の制度にも精通している会社を選ぶことが重要です。株式会社BALANCeは、ホームページの制作を通じて流入数やリード獲得数を向上させた実績が多数あるだけでなく、補助金の申請にもワンストップで対応可能です。
補助金を活用して安くホームページ制作を行いたいと考えている方や、自社に最適な補助金を知りたいと考えている方はぜひ無料の相談、見積もりをご活用ください。
ホームページ制作に活用できる補助金を申請する際の注意点
補助金を使えばホームページ制作費の負担軽減が期待できますが、申請には注意点があります。公募期間の確認、対象条件の把握、審査落選リスクや書類準備の手間、支給時期の遅れなど、事前に知っておくべきポイントを解説します。
補助金を申請する際の注意点を理解し、対策しておくことで、補助金申請をスムーズに進められるでしょう。
公募期間を確認する
補助金の申請を検討する際は、公募期間を必ず確認しましょう。多くの補助金制度は応募締切が決められており、その期間を逃すと次の募集まで待つ必要があります。
小規模事業者持続化補助金のように年度内に複数回の公募が行われるものもありますが、各回の締切期間は決して長くないので注意が必要です。
第16回公募では開始から締切までわずか19日間しかなく、十分な準備が整わず応募を断念する事業者もいました。
また、制度によっては先着順で予算枠が埋まり、期間内でも早期に募集が締め切られるケースもあります。
こうした事態を避けるため、公募のスケジュールを事前に把握し、余裕を持って準備と申請を行うことが重要です。
申請の対象外になるケースを確認する
補助金を使ってホームページ制作を行うには、各制度の対象条件を満たしているか事前に確認しましょう。補助金ごとに対象が定められており、条件外の内容は申請しても採択されません。
販路拡大や業務効率化を目的とする補助金では、採用サイトなど売上につながらないものは対象外となることがあります。
小規模事業者持続化補助金もホームページ制作費のみでは申請できず、他の販促経費と組み合わせる必要があります。
交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため、注意しましょう。対象外の内容で申請すると、時間と労力が無駄になります。申請要項をよく読み、計画が条件に適合しているか確認しましょう。
審査に落ちる場合があることを理解する
補助金は要件を満たしていても、必ず交付されるとは限りません。応募者多数の場合、提出された事業計画を審査員が評価し、得点の高い順に採択される仕組みです。
IT導入補助金2024年の通常枠では採択率が約66%に留まっています。また、小規模事業者持続化補助金では最近の公募で採択率が40%を下回り、応募しても半数以上が採択されない状況です。
審査に落ちるケースがあることを理解した上で、採択率を上げるために事業計画を練り込むことが大切です。
不採択となっても、計画を見直して次回の公募に再挑戦できます。
申請書類を揃える際に時間や手間がかかる
補助金の申請書類を準備するには、思った以上に時間と手間がかかります。補助金ごとに様式が定められており、事業計画書や経費明細、見積書など多くの書類を用意しなければいけません。
初めての方にとって申請書の作成は負担が大きく、事業の強みや販路開拓の計画を詳細に記載する必要があります。また、商工会議所で事前確認が必要な場合もあります。
電子申請に必要なGビズIDの取得には2~3週間程度かかる場合があり、余裕を持った準備が欠かせません。期限ギリギリになって慌てて書類を揃えようとすると、不備が生じて申請が受理されないリスクも高まります。申請要件を確認しつつ、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが大切です。
補助金はホームページ制作完了後に支給される
補助金は、基本的に後払いで支給されます。いったん事業者が自己資金で全額を立て替え、制作完了後に申請手続きを経て補助金が振り込まれる仕組みです。
そのため、自己資金が不足している状況で補助金が出るからとホームページ制作を進めてしまうと、支払い時に資金が足りなくなるリスクがあります。
また、補助金によっては申請条件に一定の自己資金や資本金が求められる場合もあるため、事前に必要な資金を確保しておきましょう。
補助金を活用したホームページ制作はBALANCeにご相談ください
補助金を活用してホームページ制作を行うことで、費用負担を大きく軽減できます。ただし、ここまで述べたように申請には準備や手続きに手間がかかり、事前の綿密な計画と専門的な知識とノウハウが求められます。そのため、補助金の活用を検討する際はプロに相談するのがおすすめです。BALANCeは補助金を活用したホームページ制作を数多く手がけています。
デザイン経験豊富なスタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、デザインの方向性から補助金の活用方法まで全面的にアシストします。補助金を活用したホームページ制作を検討中の方は、ぜひBALANCeにお気軽にご相談ください。