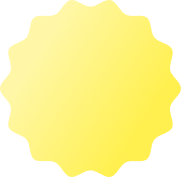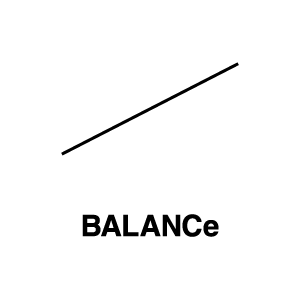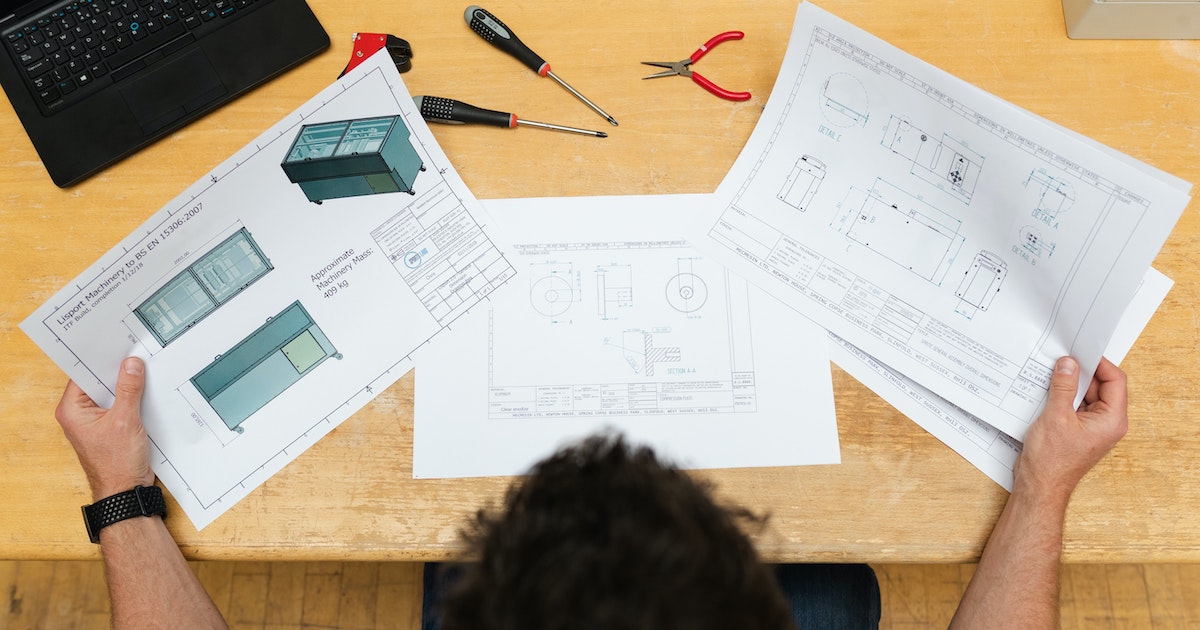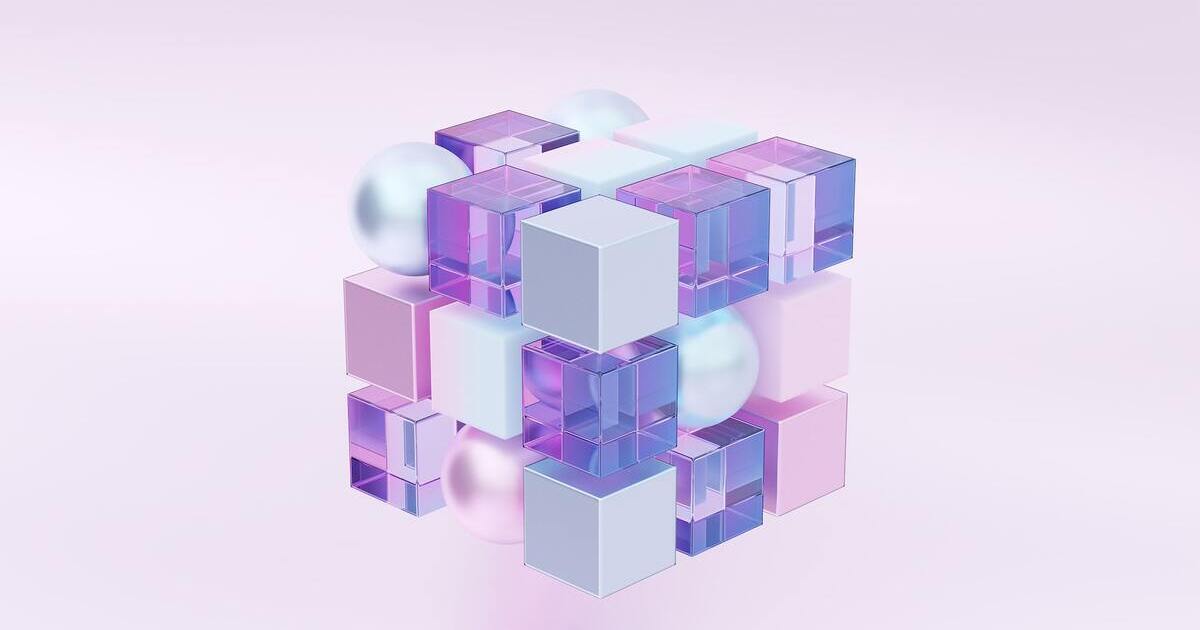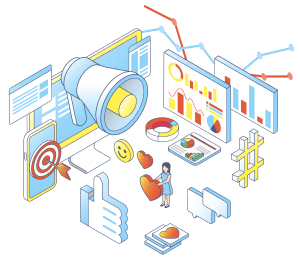Web制作会社のウェブアクセシビリティ対応とは?手順やメリットなども解説
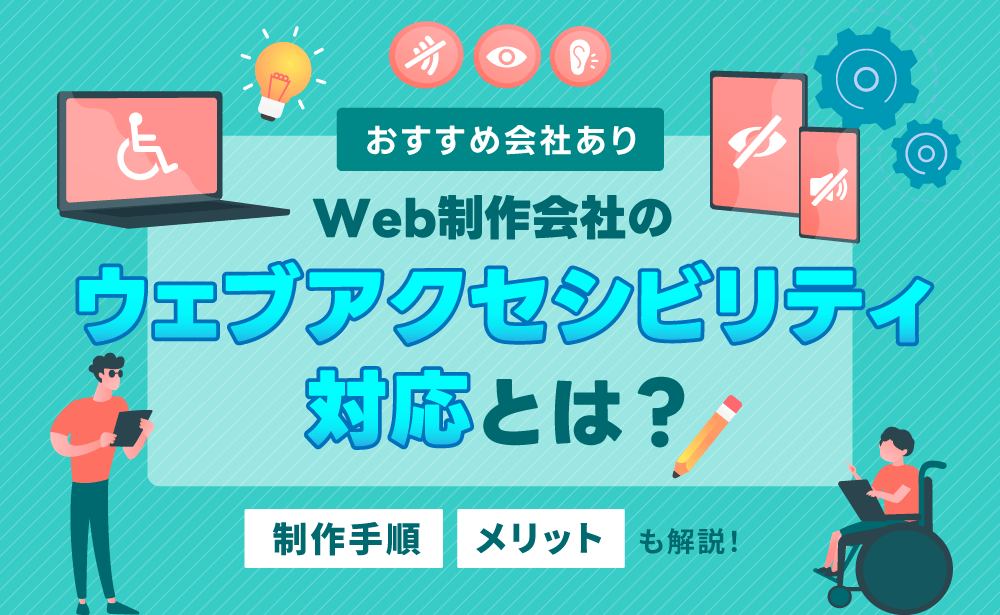
ウェブアクセシビリティ対応は、誰もが平等に情報にアクセスできる環境を実現し、企業が社会的責任を果たすうえでも欠かせない取り組みです。
しかし、「自社サイトが基準を満たしているかわからない」「どの制作会社に相談すべきか迷う」といった課題を抱える担当者も少なくありません。
この記事では、ウェブアクセシビリティの基本や必要性、対応によって得られるメリットを解説します。さらに、実績を持つ制作会社5社も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
弊社では、情報発信業務の効率化を実現するCMSや、パーソナライズされたマーケティングを実現するCRMの組み込み、ポータルサイト制作も対応可能!
メーカーや不動産企業の制作実績も多数。
ウェブアクセシビリティとは
近年は法改正により企業にウェブアクセシビリティに対する対応が求められ、確保の重要性が高まっています。ウェブアクセシビリティは企業責任として社会的意義も大きく、取り組む必然性が高いといえるでしょう。
ここでは、ウェブアクセシビリティの概要や必要性、ユーザビリティとの違いを解説します。
ウェブアクセシビリティの概要
ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障がいのある人を含め、すべての人が平等にウェブサイトの情報を利用できるようにする考え方です。
たとえば、マウスが使えずキーボード操作しかできない場合や、外出先で音声をオフにして動画を見たいときなど、一時的に操作が制限される状況でも、誰もがスムーズに情報にアクセスできることを目的としています。
企業にとっても、この取り組みは社会的責任の一部であり、誰にとっても使いやすいウェブサイトをつくることは世界的な流れになっているのです。
国際的な基準としては、「WCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines)」が定められています。これは文字の大きさや色のコントラスト、キーボード操作のしやすさなど、あらゆる利用者に配慮した設計を促す指針です。
日本では「JIS X 8341-3」という日本工業規格(JIS)があり、国内の公的機関や企業もこの基準に沿ったサイトづくりが求められています。これらの基準を踏まえて制作すると、サイト全体の品質や信頼性が高まり、検索エンジンからの評価向上にもつながります。
ウェブアクセシビリティの必要性
ウェブアクセシビリティが求められるのは、法的な義務であると同時に、企業が社会的責任を果たすためでもあります。
2021年に改正された「障害者差別解消法」により、2024年4月からは民間企業も障がいのある人に対して「合理的配慮」を行うことが義務化されました。
つまり、特定の人だけが利用しにくいウェブサイトは、法的な問題に発展する可能性があるということです。
ウェブアクセシビリティへの対応は、次の3つの観点から特に重要とされています。
| 項目 | 内容 |
| 合理的配慮 | 障がいのある人から要望があった場合、企業は無理のない範囲で利用しやすくするための対応を行う必要がある |
| 環境の整備 | 利用者が不便を感じないよう、あらかじめウェブサイトをバリアフリー化しておく努力が求められる |
| ガイドラインへの対応 | 「JIS X 8341-3」や「WCAG 2.0」などの国際・国内基準に沿って設計・制作を行うことが推奨されている |
これらの取り組みにより、誰もが安心して利用できるウェブサイトを実現できます。
さらに、アクセシビリティ対応は法律を遵守するだけでなく、企業の信頼性を高め、CSR(社会的責任)活動の一環としても高く評価されます。
ユーザビリティとの違い
ユーザビリティとの違いは、対策する前提と目的にあります。
ユーザビリティは「アクセスできること」を前提に、操作性や理解しやすさを高める考え方です。ユーザビリティ向上の施策には、画面レイアウトを分かりやすくする、操作手順を簡素化するなどがあります。
一方、ウェブアクセシビリティは、誰もが情報に到達できる状態を事前に確保する点に重きを置きます。まずウェブアクセシビリティで土台を整え、その上でユーザビリティを高める順序が基本です。そのため、ウェブアクセシビリティはすべての利用者に欠かせません。
アクセシビリティ対応では、画像に代替テキストを設定する、キーボードのみで操作可能に設計するなど、障がいの有無を問わず利用可能にする工夫が必要です。
弊社ではウェブアクセシビリティの知見を用いた誰でも使いやすいWebサイトの構築を得意としています。弊社のWebサイト制作事例やサービス概要についてはこちらからご確認ください。
BALANCeのサービス
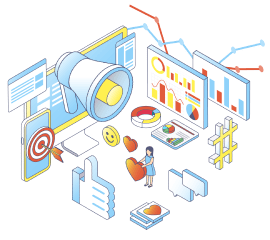
ブランディング、リード獲得のためのWebサイトを制作いたします。
マーケティング上の数値向上を最優先に、機能性とデザイン性が両立した制作・開発を行います。
ウェブアクセシビリティに対応するメリット
ウェブアクセシビリティに対応するメリットは、利用者と企業の双方にあります。
対応することで、すべての人がサイトを使いやすくなるだけでなく、企業にも大きな効果をもたらします。ここでは、ウェブアクセシビリティ対応のメリットを詳しく解説します。
誰でも情報を取得できるようになる
誰でも情報を取得できるようになることは、ウェブアクセシビリティ対応の大きなメリットです。
視覚や聴覚、身体、認知に障がいがある人や高齢者でも、適切に設計されたサイトなら円滑に情報にアクセスできます。例えば、災害時の避難場所情報など重要な内容も、アクセシビリティ対応により誰一人取り残さず届けられます。
さらに、読みやすい文字サイズや十分なコントラスト、分かりやすいナビゲーションは障がいの有無を問わず使いやすく、サイト全体のユーザビリティ向上につながるのです。
結果として、情報発信は幅広い層に届き、誰一人取り残さない社会の実現にもつながります。
ブランドイメージが向上する
ウェブアクセシビリティへの取り組みは、企業の信頼性やブランドイメージを高める大きな効果があります。
アクセシビリティ対応とは、誰にとっても使いやすいウェブサイトをつくることを目的とした取り組みです。これは企業が社会の一員として、「すべての人に配慮する姿勢」を示す行動でもあります。
近年では、多くの企業がこうした活動をCSR(企業の社会的責任)の一環として実施しています。CSRとは、法律を守るだけでなく、社会や環境への貢献を重視して行動する考え方です。
障がいのある方や高齢者を含むあらゆる人が使いやすいウェブサイトを運営するのは、企業が「誰にでも開かれた存在」であると、社会に示すことにつながるのです。
その結果、利用者からの信頼が高まり、企業のイメージや評価も向上します。さらに、「人に優しい企業」として共感を得ることで、他社との差別化や顧客のファン化にも結びつきます。
検索エンジンの評価が向上する
検索エンジンの評価が向上することも、ウェブアクセシビリティ対応の大きなメリットです。
適切なHTML構造や代替テキストの設定など、基準に沿ったマークアップは検索エンジンのクローラーに内容を正しく理解させます。例えば、画像に代替説明を付与すれば、その情報が検索結果に反映されやすくなります。
さらに、わかりやすいサイトは人間にも機械にも読み取りやすく、Googleのガイドラインにも適合します。その結果、SEOにおいて有利に働き、検索順位の向上や自然検索からの流入増加につながります。
訴訟リスクへの対策になる
訴訟リスクへの対策になることも、ウェブアクセシビリティ対応のメリットです。特にアメリカでは、アクセシビリティを巡る訴訟件数が年々増加しています。米国の障害者法(ADA)に基づき、視覚障がい者から利用しにくいとされ大手企業が訴えられる事例もあります。
そのため、「誰もがアクセスできるサイト」であることが国際的な標準となりつつあります。
グローバルに事業を展開する企業にとって、各国の法規制に対応しアクセシビリティを確保することは法的トラブルを防ぐうえで不可欠です。現状、日本では訴訟件数は欧米ほど多くありませんが、将来的に法規制強化や社会的要請の高まりによってリスクが拡大する可能性があります。そのため、早期対応が訴訟リスク軽減の有効な手段です。
ウェブアクセシビリティに対応できる制作会社5選
ウェブアクセシビリティに対応できる制作会社5選は、信頼性と実績を重視して選ぶことが重要です。デジタル社会の進展に伴い、対応は一層重要視されるようになりました。
近年は法的にも義務化され、公共サイトに限らず一般企業のサイトにも求められています。ここでは、アクセシビリティに強みを持つ制作会社5社を紹介します。
株式会社BALANCe

株式会社BALANCeは、機能性とデザイン性を融合させたウェブ制作を強みとしています。
ユーザビリティとクリエイティブを両立させたサイト構築を得意とし、会員管理や予約システムなど高度な機能実装の実績も豊富です。
ノウハウを活かし、ウェブアクセシビリティに配慮した高品質なサイトを実現します。
コーポレートサイトから大規模な案件までさまざまな実績を持っています。さらに、自治体の採用サイト構築など公共分野での実績もあり、ウェブアクセシビリティのガイドラインに準拠した制作にも対応可能です。誰もが情報にアクセスしやすいサイト制作を提供しています。
アイレット株式会社

アイレット株式会社は、KDDIグループのIT企業としてウェブアクセシビリティ向上に積極的に取り組んでいます。自社サイトではWCAG 2.2レベルAA準拠を目標に掲げ、誰もが使いやすいサービスの実現を推進しています。
具体事例として、ローランド社の新規システム開発ではUI/UX設計から実装までアクセシビリティ対応を徹底しました。画面設計やデザイン、コーディングの各段階で自動ツール(axe)検証と音声読み上げによる手動チェックを実施し、代替テキストやキーボード操作対応を丁寧に実装しています。
さらに、ブランドイメージを損なわない複数のデザイン案を提示し、視認性とデザイン性の両立を追求。このプロジェクトで得た知見は今後の開発にも活かされ、誰もが使いやすいサービス提供に貢献しています。
WANTMORE株式会社

WANTMORE株式会社は、誰にとっても使いやすいWebを目指すアクセシビリティ支援を主要事業とする制作会社です。2020年設立で、障がい者や高齢者を含む幅広い利用者に配慮した取り組みを展開しています。
形式的な対応に留まらず、本質的なユーザビリティ向上を重視する姿勢が特徴です。障がい者支援施設と連携し、実際の当事者によるサイト検証体制を構築。ガイドラインでは捉えきれない生の声を反映し、改善を推進しています。この検証体制は、新たな雇用創出にもつながる独自の取り組みです。
株式会社 シスコム
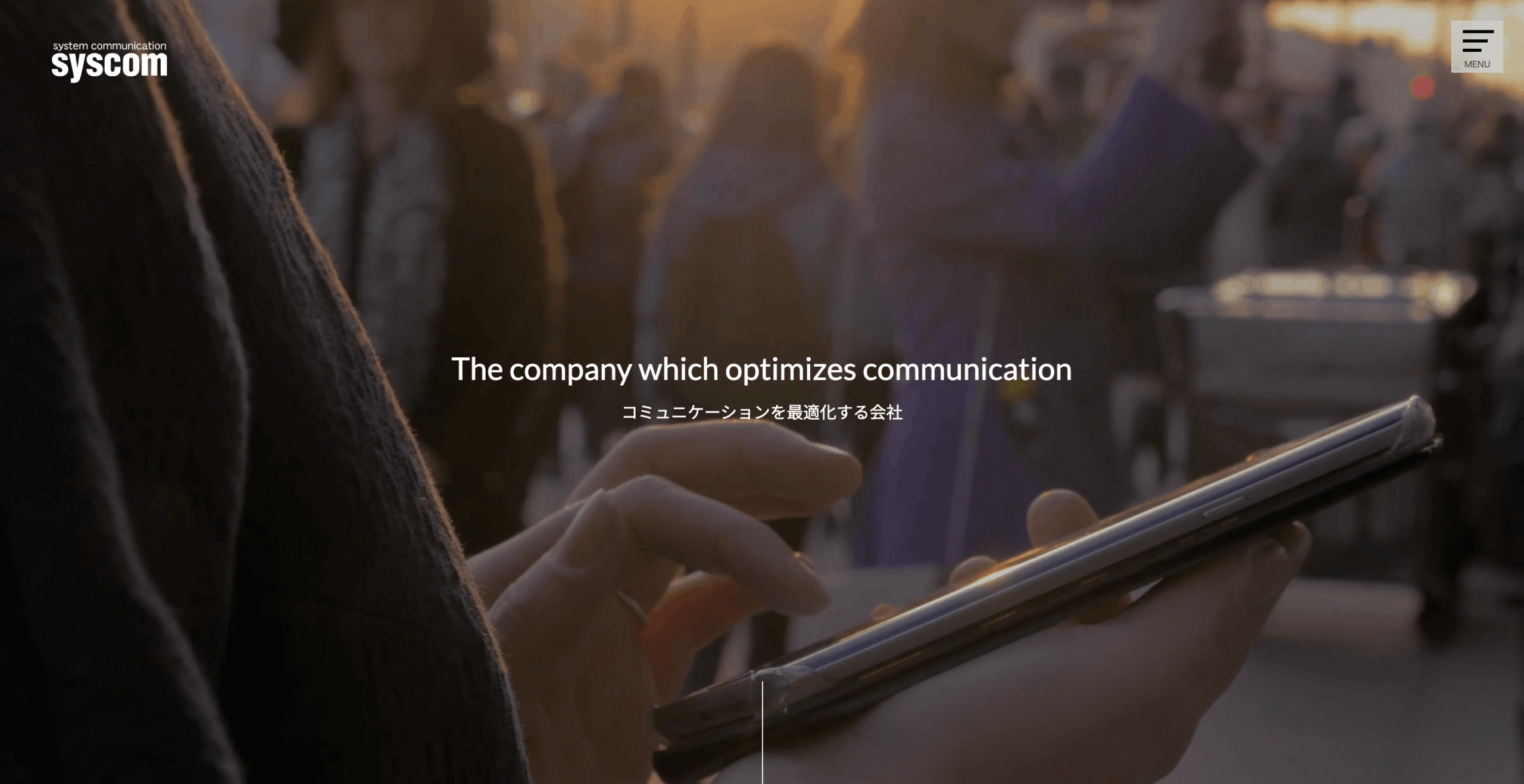
株式会社シスコムは、銀座に本社を置きウェブアクセシビリティ対応支援に注力するWeb制作会社です。2021年の法改正で確保が努力義務から法的義務に変わった点を踏まえ、アクセシビリティを企業の社会的責任の一環と位置付ける動きが広がっていると伝えています。
同社は、公的機関サイトではレベルAA、一般企業サイトでも最低レベルA準拠を目標とすることを推奨しているのです。JIS X 8341-3やWCAGなど明確な基準に沿った対応を提案しています。
適切なマークアップによる改善はサイト全体の品質向上に直結し、検索エンジン最適化にも有効です。シスコムはこれらの知見を活かし、すべての利用者が等しく情報にアクセスできるWebサイトの実現を支援しています。
株式会社ミツエーリンクス

株式会社ミツエーリンクスは、Web制作分野で長年の実績を持ち、ウェブアクセシビリティへの取り組みを積極的に進めている企業です。WCAG 2.2やJIS X 8341-3といった最新ガイドラインへの準拠を掲げ、構築時だけでなく公開後の定期診断を通して品質維持と向上を実現します。
運用段階で見落とされがちな課題にも対応し、構築時の投資を無駄にしない継続支援を提供しているのです。専門チームが診断やコンサルティング、実装支援から運用時のチェックまでをワンストップで対応します。
さらに、自動検査ツール(axe Monitor)の活用や社内外向けセミナーを実施し、啓発活動にも注力しています。また、アクセシビリティBlogで国内外の最新情報やノウハウを発信し、企業や社会全体の意識向上に貢献しているのです。
東京にあるホームページ制作会社についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
ウェブアクセシビリティに対応したサイトを制作する手順
ウェブアクセシビリティに対応したサイトを制作する手順は、計画から運用までを管理することが大切です。
制作会社が進める際は、まず現状を把握し、課題を明確化します。そのうえで、デザイン・実装・検証・改善の循環を設計しましょう。ここでは、実務の工程を段階ごとに解説します。
1.現状を把握する
ウェブアクセシビリティ対応を進めるうえで、まず重要なのは「現状を正確に把握すること」です。
はじめに、自社サイトがどの程度アクセシビリティに配慮できているかを確認し、課題を整理します。その際は、サイトの目的や主な利用者層を明確にし、どのような人が利用しにくさを感じているのかを把握することが大切です。
次に、どの基準(例:JIS X 8341-3やWCAG 2.0など)に基づいて改善を進めるかを決め、対応範囲を設定します。また、自動チェックツールや専門家による診断を活用して、問題点を具体的に洗い出します。
こうした調査を通して、優先的に改善すべき部分を明確にし、効果的なアクセシビリティ向上の方針を立てられるのです。
2.デザイン・実装を行う
デザインや実装の段階では、見た目の美しさだけでなく、すべての利用者が使いやすいサイトを構築する意識が重要です。
デザイン面では、色の見え方や文字の読みやすさに配慮し、コントラスト比やフォントサイズを適切に設定します。どのデバイスでも快適に閲覧できるよう、レスポンシブデザインを採用することも基本です。
実装面では、正しいHTMLタグを使用して文書構造を明確にし、スクリーンリーダーなどの支援技術で正しく内容が読み取れるようにします。画像には代替テキストを設定し、キーボード操作だけでもすべての機能を利用できるよう設計します。
さらに、必要に応じて多言語対応や音声読み上げ機能を導入し、より多様なユーザーが快適に利用できる環境を整えることが理想的です。
3.アクセシビリティチェックを行う
デザインや実装が完了したら、ウェブサイト全体のアクセシビリティを確認します。チェックは、自動検査ツールと目視確認の両方を組み合わせて行うことが効果的です。
自動ツールでは、HTMLの文法エラーや画像の代替テキストの有無など、機械的に判断できる項目を確認します。
一方、スクリーンリーダーによる読み上げテストやキーボード操作の動作確認など、人による手動テストも欠かせません。特に、コントラスト比の確認には「Color Contrast Analyzer(CCA)」などのツールを使い、文字の視認性を確かめます。
さらに、W3Cが提供する「Markup Validation Service」を利用してHTMLやCSSの構文エラーを修正し、サイト全体の品質を向上させます。最終的には、JIS X 8341-3:2016やWCAGなどの基準に照らして適合度を評価し、改善点を明確にすることが重要です。
4.運用・改善を行う
ウェブアクセシビリティ対応は、サイトを公開して終わりではなく、継続的な運用と改善が欠かせません。
まず、定期的にアクセシビリティチェックを実施し、法改正やガイドラインの更新に合わせて修正を行います。新しいコンテンツを追加する際も、画像の代替テキストやコントラスト比などの基準を守ることが大切です。
また、アクセス解析を活用して、利用者がどのようにサイトを操作しているかを把握します。離脱が多いページや操作しづらい箇所を特定し、改善につなげることで、より快適な利用環境を維持できるのです。
さらに、定期的なバックアップやセキュリティ対策を行い、サイト全体の安全性と安定性を確保します。こうした運用段階での継続的な改善を重ねることで、アクセシビリティと使いやすさを両立したウェブサイトを長期的に維持できます。
弊社では、ウェブアクセシビリティに配慮したWebサイト制作の提案をさせていただきます。もちろん、見積もりとご提案は無料です。予算が決まっていない場合もぜひこちらからお問い合わせください。
弊社では最新テクノロジーを活用したサイト制作も対応可能!
お見積もりやご提案はもちろん無料です。ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。
ウェブアクセシビリティ対応の基本となる10項目
ここでは、ウェブアクセシビリティ対応の基本となる10項目を紹介します。弊社ではすべて対応可能なので、ぜひ参考にしてください。
ページの内容を把握できるページタイトルを記載する
HTMLの<title>要素を適切に設定すると、ユーザーはページを開いた瞬間に内容を把握できます。
特にスクリーンリーダーを利用する方にとって、ページタイトルは最初に読み上げられる重要な情報です。そのため、「サービス概要|会社名」など、ページの目的と位置づけが一目でわかる明確な表現が必要です。
タイトルが抽象的だと、ユーザーは目的のページを見つけにくくなります。弊社では、SEOとユーザビリティの両面を考慮し、誰にとっても直感的に理解できるタイトル設計を徹底しています。
見出しやリストなどの文書構造をマークアップする
ページ内の情報を正しく伝えるためには、見出しやリストを文書構造に沿ってマークアップすることが重要です。
<h1>から<h6>までの見出しタグを階層的に使用すると、内容の関係性が明確になり、スクリーンリーダー利用者も目的の項目へスムーズに移動できます。
また、箇条書きや番号付きリストには<ul>や<ol>タグを用いることで、情報を整理できるため読みやすさを向上できます。
画像に代替テキストを記載する
画像には必ず代替テキストを設定し、視覚に頼らず内容を理解できるようにしましょう。
<img>タグのalt属性に記述されたテキストは、画像が表示されない場合やスクリーンリーダー使用時に読み上げられます。装飾目的の画像には空のaltを設定し、情報を持つ画像には内容や意味を簡潔に記述することで、利用者に正確な情報を伝えられます。
テキストリンクにはリンク先がわかるテキストを記載する
リンクテキストは、クリックした先でどのような情報が得られるのかを明確に示すことが大切です。
「詳しくはこちら」や「ここをクリック」といった曖昧な表現では、スクリーンリーダー利用者にとって内容を判断しにくくなります。そのため、「サービス内容を見る」「お問い合わせフォームはこちら」など、リンク先の目的を具体的に表すテキストにすることが大切です。
サイト全体のコントラスト比を意識する
文字と背景のコントラスト比を適切に保つことは、読みやすさを確保するうえで重要です。
特に、色覚に制限のある方や視力が低下している方でも文字を判別しやすくするためには、少なくとも4.5:1以上のコントラスト比を維持することが推奨されています。
背景と文字の色が近いと、内容が見えづらくなることがあります。たとえば、薄いグレーの文字を白い背景に配置すると、多くの人にとって視認性が低下するのです。
一方、黒文字に白背景など明暗の差が明確な配色は、誰にとっても見やすい組み合わせとなります。
さらに、リンクやボタンなどの操作要素も、色だけで区別せず、下線や形状の違いなど複数の手がかりを組み合わせることが望ましいです。
このように、デザイン全体でコントラストと視認性を意識すると、誰もが快適に利用できるサイトを実現できます。
フォームコントロールのラベルや説明をマークアップする
入力フォームには、<label>要素やtitle属性を用いてラベルを正しく関連付けることが重要です。スクリーンリーダーが項目名を正確に読み上げられ、視覚に頼らず入力内容を把握できます。また、ラベル部分をクリックして入力欄を選択できるため、操作性も向上します。
コンテンツは拡大表示できるようにする
コンテンツは、ブラウザの拡大機能を使用してもレイアウトが崩れないよう設計することが重要です。
特に視力が低下した方や高齢の利用者が読みやすいよう、相対的な文字サイズ指定を採用し、拡大時も文字の重なりや操作の妨げがないかを確認します。
キーボードだけで操作できる設計にする
マウスを使用できないユーザーのために、キーボード操作だけで全ての機能を利用できるよう設計することが重要です。
リンク移動やボタン操作、フォーム入力などを「Tab」キーや矢印キーでスムーズに操作できるようにし、フォーカス位置を視覚的に分かりやすく示します。
エラーメッセージではエラー箇所と修正方法を明示する
エラーメッセージは「入力エラー」などの抽象的な表現は避けるべきです。「電話番号が全角で入力されています。半角で入力してください。」のように、誤りの内容と修正方法を具体的に示すことが重要です。
動画ではキャプション(字幕)を提供する
音声付きの動画にはキャプション(字幕)を追加し、聴覚に障がいのある方や音を出せない環境でも内容を理解できるようにします。すべてのユーザーが、等しく情報を得られる設計が重要です。
ウェブアクセシビリティの制作は株式会社BALANCeにご相談ください
ウェブアクセシビリティ対応は、誰もが平等に情報にアクセスできる環境を整える重要な取り組みです。障がいの有無や年齢を問わず利用可能な設計は、社会的責任を果たすだけでなく企業価値や信頼性の向上にもつながります。
さらに、検索評価の改善や訴訟リスクの低減など実務面での効果も大きく、導入は今後ますます必須となるでしょう。
株式会社BALANCeは、企画力と開発力を強みとする渋谷拠点のWeb制作会社です。高度なシステム実装からデザイン性の高いサイト構築まで幅広く対応し、最新技術と豊富なノウハウでアクセシビリティ配慮を実現します。公共案件や企業サイトの実績も豊富で、誰もが使いやすいウェブサイトを提供します。
ウェブアクセシビリティ対応の制作は、ぜひBALANCeにご相談ください。