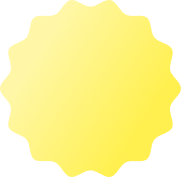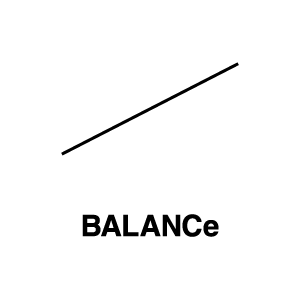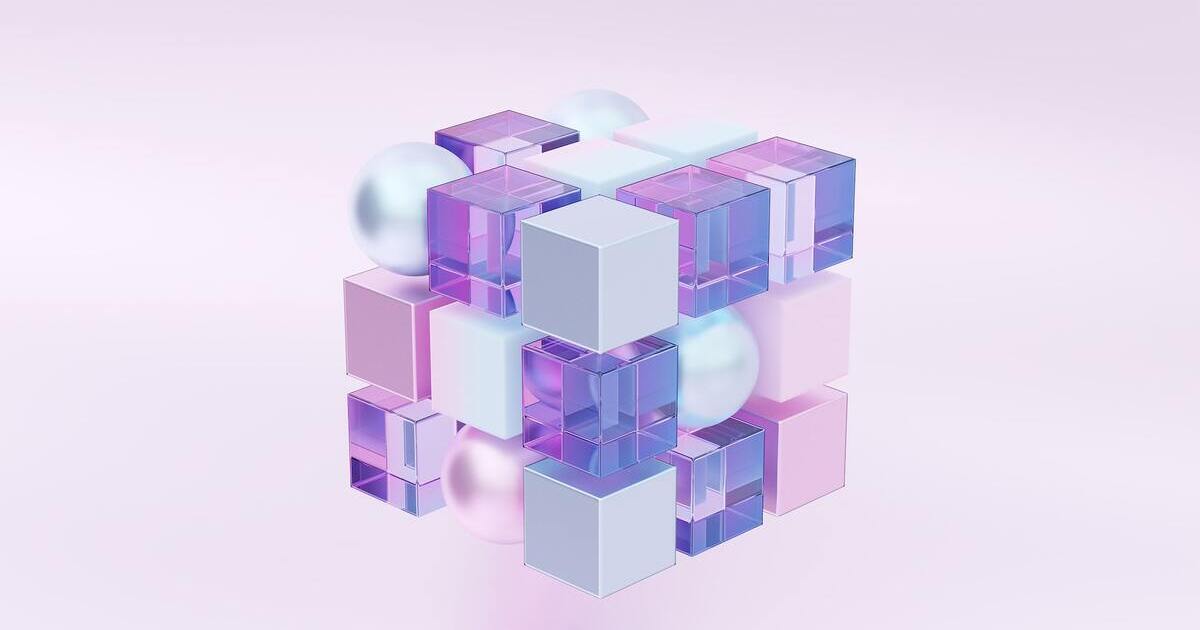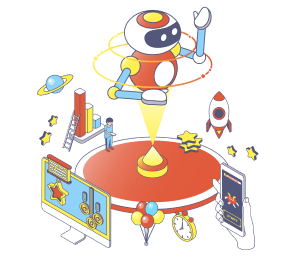ゲーミフィケーションの導入事例を紹介!ゲームコンテンツの種類や導入の流れも解説

ゲーミフィケーションとは、本来ゲームではない場面にゲームの仕組みを取り入れる手法です。
施策やサービスにゲームの仕組みを取り入れることでユーザーの関心を引きつけられるため、ゲーミフィケーションは様々な企業から注目を集めています。
ただし、ゲームコンテンツの種類は豊富にあります。どのようなゲームコンテンツをどのように取り入れればよいかわからない、という担当者の方もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では、ゲームコンテンツ導入の事例と成功に導くための導入ステップについて詳しく解説します。
弊社では、webサービス、アプリの開発、特に、ARやメタバース、3D表現などを使ったリッチなコンテンツ、ゲームコンテンツにも対応可能!大手エンタメ会社やアパレルハイブランドでの制作実績も多数。
ゲーミフィケーションとは
ゲーミフィケーションとは、本来ゲームではない場面にゲームの仕組みを取り入れる手法です。企業の視点では、キャンペーンやサービスに遊びの要素を加えることで、ユーザーにとって魅力的な体験を提供できるメリットがあります。
ユーザーの視点では、ゲーム感覚でサービスを利用できるため、楽しみながら参加できる点がメリットです。
また、教育やマーケティングなど様々な分野で活用が進んでおり、学習意欲の向上やユーザー行動の促進といった効果も報告されています。
このように、ゲーミフィケーションは企業・ユーザー双方に価値をもたらす取り組みとして注目されています。
弊社ではゲームを活用したWebサイトやサービスの企画・制作を得意としています。ゲームを活用したコンテンツの制作事例やサービス概要についてはこちらからご確認ください。
BALANCeのサービス
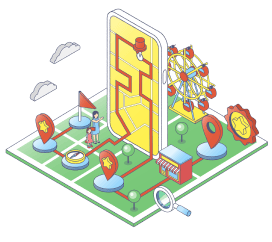
目を引くデザインと演出で関心を喚起するキャンペーンサイト・周年サイトや、AR、メタバース、AIといった最新技術を駆使したPRコンテンツや常設コンテンツを制作・開発いたします。
ゲームコンテンツを活用するメリット
企業がマーケティングにゲームコンテンツを取り入れることで期待できるメリットは様々です。具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここからは、ゲーミフィケーション導入によって得られる主なメリットを見ていきます。
企業・サービスの理解につながる
ゲームの要素を取り入れることで、ユーザーに自社サービスの内容や魅力を効果的に理解してもらいやすくなります。なぜなら、クイズやミニゲームといった双方向の仕掛けからユーザーが楽しみながら商品情報や使い方を学べるためです。
文字だけの説明よりも記憶に残りやすい効果があります。例えば、化粧品メーカーが肌診断クイズを提供し、数問の質問に答えるとユーザーに合った商品を提案されるという仕組みです。
ゲーム感覚で自分に最適な製品を知ることができ、楽しみながらブランドへの理解を深められます。このように、遊びの要素を通して情報提供すると、ユーザーにサービス内容を自然に理解してもらう効果が期待できます。
ユーザーデータ(属性情報)を獲得できる
ゲームコンテンツを通して、ユーザーの属性や興味に関するデータを自然に収集できます。理由として、ゲーム参加時に必要な登録情報や、プレイ中の行動履歴が蓄積されるためです。
ゲーム内でポイントを獲得する頻度や選択した行動パターンを分析すれば、ユーザーの嗜好や関心を把握できます。これにより、蓄積データをもとにターゲットを絞ったマーケティングや、一人ひとりに合わせたプロモーション施策につなげられます。
ユーザーを楽しませながら貴重な情報を収集すれば、得られたデータでマーケティング効果を高められるでしょう。
キャンペーン・PRでの拡散につながる
ゲームコンテンツを活用すると、キャンペーンやPR施策がSNSで拡散されやすくなります。ユーザーがゲームの成果を共有したり、友人に勧めたりしたくなる心理が働くからです。
また、面白いゲーム体験は自然と口コミで広がります。楽しい競争や報酬があると、ユーザー自ら積極的に結果をSNSに投稿する傾向があります。
あるキャンペーンでは、多くの参加者がゲームのクリアタイムや画面をX(Twitter)に投稿し、大きな話題となりました。このように、ゲーム要素を取り入れるとユーザーが広告塔となり、企業は自然な形で認知拡大につなげられます。
リピート率の向上につながる
ゲームの仕組みを取り入れることで、ユーザーのサービス利用頻度が上がり、リピート率の向上につながります。ポイント獲得やランクアップなど、継続した利用を促すインセンティブを設計できるためです。
購入ごとにポイントが貯まるデジタルスタンプカードは、楽しみながらポイント収集ができるため再来店を促進します。
また、友達に紹介した側も、された側も特典がもらえる仕組みにすれば、新規顧客の獲得と既存顧客の継続利用の双方に効果があります。
ゲーム性を持たせたインセンティブによって顧客のロイヤリティを高め、長期的なリピーターの確保につなげられるでしょう。
弊社では、マーケティングに役立つゲームコンテンツの制作を得意としています。ご相談やご提案は無料なので、ぜひ制作を検討している方はこちらからご相談ください。
弊社では業務効率化やマーケティングを考慮したシステム開発も対応可能!お見積もりやご提案はもちろん無料です。ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。
ゲームコンテンツの種類
ゲームコンテンツを活用すると、ユーザーの関心や理解を深め、商品やサービスの訴求力を高められます。
また、従来の広告との差別化や顧客エンゲージメント向上の手法としても効果が期待できるでしょう。ここからは、目的別にゲームコンテンツの種類を紹介します。
サービス・商品理解促進目的のゲームコンテンツ
ユーザーにサービスや商品の理解を深めてもらうことを目的としたゲームコンテンツです。
クイズゲームやシミュレーションなどを通して、楽しみながら商品情報を伝える手法が含まれます。顧客の理解度を高め、商品への興味や納得感を引き出す狙いがあります。
クイズゲーム
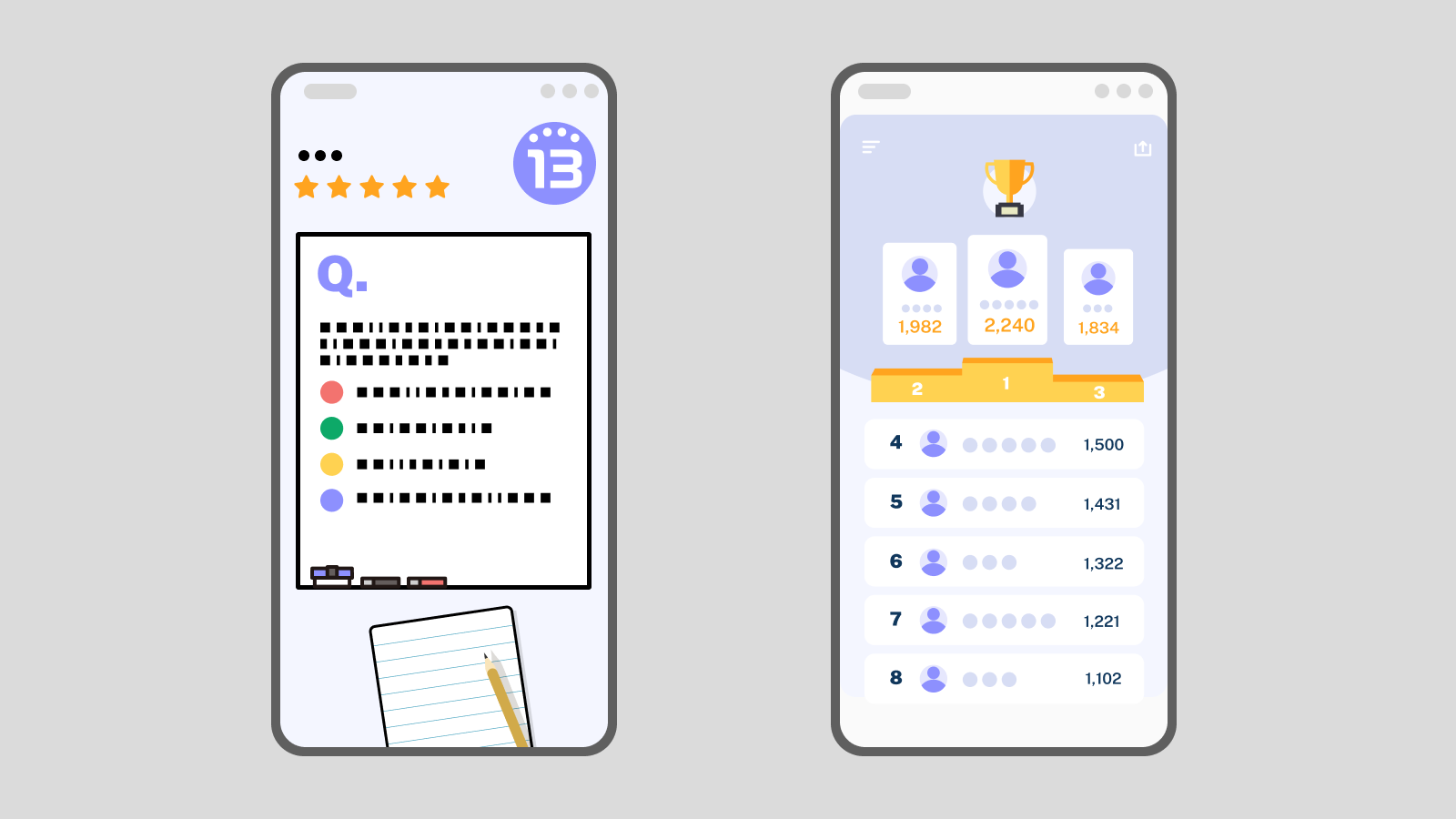
| 制作予算 | 約50万〜1,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
クイズゲームは、ユーザーがクイズに回答しながら商品やサービスに関する知識を深められるゲームコンテンツです。クイズ形式で情報を出題すると、ユーザーは楽しみながら自然に商品特徴やメリットを学べます。
例えば、新商品の機能やブランドの歴史をクイズに盛り込み、全問正解者にクーポンを提供すれば、遊びを通して理解促進と認知度向上の両方が期待できます。
このように、クイズゲームはサービス理解を深めるだけでなく、ユーザーの興味を喚起しブランドへの愛着を高める効果があるのです。比較的シンプルな仕組みのため、導入のハードルが低い点も魅力です。
ドライブゲーム
| 制作予算 | 約150万〜3,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
ドライブゲームは、ユーザーが車やキャラクターを操作してコース上を進むタイプのゲームコンテンツです。レースや街巡りの要素を取り入れることで、ユーザーに爽快感と達成感を与え、長時間のプレイによってブランド名や商品を印象付ける効果があります。
自動車メーカーが自社の車種を使ったレーシングゲームを提供すれば、ユーザーは遊びながら製品の魅力や性能を疑似体験できます。
また、街中のポイントを通過するとキャンペーン情報が表示されるなど、ゲーム内で商品に関するメッセージの掲載も可能です。
ドライブゲームは楽しい体験から認知拡大・ブランディングに大きく貢献します。ただし、凝った演出や高度な開発が必要な場合、他のコンテンツよりも制作コストが高くなる点に注意が必要です。
パズルゲーム

| 制作予算 | 約50万〜1,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
パズルゲームは、ユーザーが頭を使って問題を解くタイプのゲームコンテンツです。マッチングパズルや謎解きなど、商品やサービスに関連した要素を組み込むと、ユーザーに楽しみながらブランドに触れてもらえます。
ユーザーはパズルに集中する過程で、自然と商品名や特徴に触れる機会が増えるでしょう。結果として、認知度や商品理解の向上が期待できます。化粧品ブランドが成分や効能をテーマにしたパズルを提供し、クリアしたユーザーに限定クーポンを配布すれば、ゲームを通して商品の魅力を伝えつつ購買意欲を高められます。
パズルゲームはユーザーの興味を引きつけながら認知度・売上の向上につながる効果的な手法です。比較的シンプルなゲームが多いため、実装のハードルが低い点も魅力です。
認知向上目的のゲームコンテンツ
商品やブランドの認知度を高めることを目的としたゲームコンテンツです。SNSで拡散しやすいユーザー参加型の企画を通して、多くの人にブランド情報を届けます。
代表的な例として、人気投票やランキング形式のコンテンツが挙げられます。
人気投票・ランキング

| 制作予算 | 約300万〜3,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
人気投票・ランキングは、ユーザーにお気に入りの商品やキャラクターなどへ投票してもらい、その結果をランキング形式で発表するゲームコンテンツです。シンプルな仕組みですがユーザーが主体的に参加できるため熱中しやすい点が特徴です。投票結果をSNSで共有したくなる傾向があり、自然とオンライン上で話題が広がります。
飲料メーカーが製品ラインナップの中で「人気フレーバー投票」を実施すれば、ファンが互いに投票を呼びかけ合うなど、SNS上で盛り上がりが期待できるでしょう。その結果、商品の認知度向上に直結し、注目度の高まった商品は売上アップにもつながります。
人気投票やランキング企画は、SNSでの拡散による認知拡大と購買意欲の喚起に効果的です。ただし、仕組みを構築するにはコストと時間がかかる点に注意が必要です。
周遊・回遊目的のゲームコンテンツ
ユーザーに実際の施設や観光地を巡ってもらったり、Web上で回遊を促したりすることを目的としたゲームコンテンツも存在します。
デジタルスタンプラリーのように、ゲーム感覚で各スポットを巡る仕組みを取り入れると、楽しみながら行動を促せます。
デジタルスタンプラリー

| 制作予算 | 約50万〜3,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
デジタルスタンプラリーは、従来の紙台紙によるスタンプ集めをデジタル化したもので、スマートフォンを使って指定されたスポットを巡り、電子スタンプを集めるゲーム性のある施策です。
スタンプをすべて集めるために複数の場所を訪れる必要があるため、自然とユーザーの回遊率が向上し、特定エリアへの集客につながります。
また、ゴール達成時にクーポンや特典を提供すれば、リピート来訪を促進し売上向上も期待できます。例えば、商店街が各店舗にスタンプを設置し、全店分のスタンプを集めた参加者に景品を用意すれば、ユーザーは楽しみながら商店街全体を巡り、購買も活性化するでしょう。
デジタルスタンプラリーはゲーム感覚でユーザーの行動を喚起し、リピート率・売上向上に効果的なコンテンツです。専用システムの開発が必要になるため、規模によって費用と期間が大きく変動する点には注意が必要です。
販売促進目的のゲームコンテンツ
商品購入や来店頻度の向上を狙った販売促進目的のゲームコンテンツです。遊びの要素と景品を組み合わせ、ユーザーの継続利用や購買意欲を刺激する施策が含まれます。
代表例として、ガチャゲームが挙げられます。
ガチャゲーム
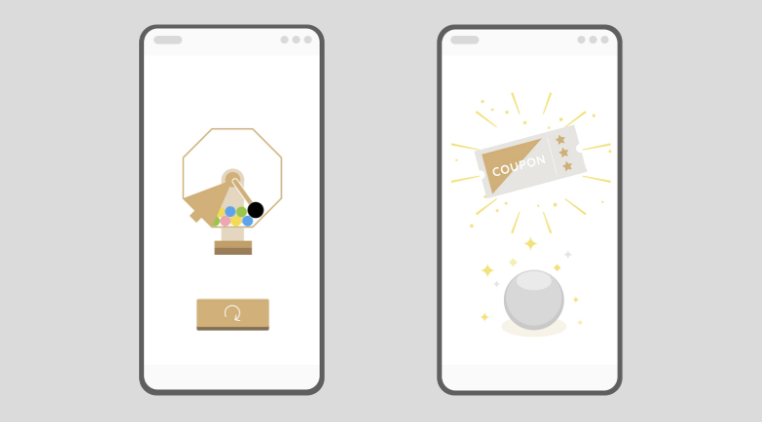
| 制作予算 | 約50万〜1,000万円 |
| 制作期間 | 約2ヶ月〜 |
ガチャゲームは、カプセルトイのようにランダムな景品が当たる抽選要素を取り入れたゲームコンテンツです。ユーザーは何が当たるか分からないワクワク感から、繰り返し挑戦したくなる心理が働きます。
企業のキャンペーンでは、毎日1回無料で引けるデジタルガチャや、購入・来店時に参加できるガチャなどがよく活用されます。例えば、ECサイトが日替わりでポイントやクーポンが当たるガチャを設置すれば、ユーザーは毎日サイトを訪れて挑戦するようになり、結果的に購買頻度も増えるでしょう。
また、一定金額の購入ごとにガチャチケットを配布すれば、さらなる買い物を促進できます。ガチャゲームはユーザーのリピート率を高め、売上向上に貢献する効果的な手法です。
比較的シンプルな仕組みですが、景品管理や不正対策の導入には一定のコストと期間が必要です。
ゲームコンテンツの活用がおすすめの業界
実際に様々な企業が顧客エンゲージメント向上や売上増加を目的に、ゲームコンテンツを導入し始めています。
ここからは、特にゲームコンテンツの活用がおすすめの業界を紹介します。
食品業界
食品業界では、自社商品のプロモーションにゲームコンテンツを取り入れることで、消費者の興味関心を高める効果が期待できます。ゲーム世代である若年層に、アピールする手段としても有効です。
単なる広告ではなくミニゲームやクイズを提供し、遊びながら商品に触れてもらうことで、ユーザーの記憶に残りやすくなります。Web上で遊べるシューティングゲームをキャンペーンとして展開し、スコアに応じて割引クーポンやポイントを付与すれば、参加者は高得点を目指して熱中しつつ、クーポンで商品を購入してみようと意欲が湧きます。
さらに、ゲームで高得点や景品を獲得したユーザー体験はSNSで共有されやすく、キャンペーン全体の認知拡大にもつながるでしょう。
ゲームの結果に応じたインセンティブ(報酬)を用意する施策により、消費者は楽しみながら企業の施策に参加し、最終的には購買行動へとつながりやすくなるのです。
飲食業界
飲食業界では、顧客に繰り返し来店してもらい、満足度を向上させるためにゲームを活用する事例が増えています。食事そのものに加えてゲーム性を持たせると、来店体験がより楽しいものとなり、リピーター獲得につながります。
回転寿司チェーンでは、寿司皿5枚ごとにガチャ抽選に挑戦できる「ビッくらポン!」というゲームを導入し、当たりが出れば景品がもらえる仕組みを作りました。この施策により、ゲーム目当てで何度も来店する顧客も現れ、売上向上につながっています。
また、デジタルスタンプラリーを活用し、来店ごとにスタンプを付与して一定数集めると特典を提供するなどの施策も有効です。ガチャ型のクーポン配布などランダム要素を取り入れると、毎回違う景品への期待感から顧客の来店意欲が高まります。
さらに、店舗の待ち時間にスマホでクイズやミニゲームを楽しめるようにすれば、待ち時間の退屈さが軽減され、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
自治体
自治体においても、観光客集客のためにゲームを活用するメリットがあります。旅行者に地域を巡ってもらう仕掛けとして、デジタルスタンプラリーは有効です。
観光地や地元店舗に設置されたQRコードをスマホで読み取ってスタンプを集めるデジタルラリーを開催すれば、遊び感覚で複数のスポットを回ってもらえます。
紙の台紙を持ち歩く必要がなくスマートフォン一つで気軽に参加できる点も、利用者にとって魅力です。参加者はスタンプをコンプリートすると記念品や特典が得られるため、地域内の様々な場所を訪れるモチベーションが生まれます。
実際に、ある自治体では市内の飲食店や観光施設を巡るスタンプラリーを導入し、新たな観光資源の発掘や地域経済の活性化を実現しています。
ゲームコンテンツを観光施策に組み込むと、訪れる人に楽しんでもらいながら地域への誘客効果を高めることができるのです。
教育業界
教育業界では、学習者のモチベーションを高めるためにゲームの要素を取り入れることが重要視されています。勉強や研修は単調になりがちですが、ゲーム性を加えることで楽しみながら継続的に取り組みやすくなるのです。
語学学習アプリ「Duolingo」ではクイズに正解するたびにポイントや経験値が貯まり、レベルアップや連続学習記録といった仕組みでユーザーのやる気を引き出しています。
ゲーミフィケーション要素により、ユーザーはゲームを進める感覚で勉強を習慣化できるでしょう。同様に企業の社員研修においても、VRやシミュレーションゲームを活用して技能を習得させる試みがなされています。
実際にKFC(ケンタッキーフライドチキン)では、VRゲーム上で調理の手順を疑似体験させる研修コンテンツを導入し、従業員の技能習熟スピードが向上したとの報告があります。
このように、学習や研修にゲームを取り入れると、受講者が主体的かつ楽しく学べる環境を作り出し、教育効果を高められるのです。
ゲームコンテンツを導入する際の流れ
ゲームコンテンツ導入の一般的なスケジュールは以下の通りです(全体期間の目安:約3〜5ヶ月)。
| 時期(目安) | 主な取り組み内容 |
| 0〜1ヶ月目 | 導入準備・企画提案:導入の目的整理、打ち合わせ・ヒアリングを経てゲーム企画を提案(約1ヶ月) |
| 2〜4ヶ月目 | 開発・実装:提案内容に基づきゲームコンテンツの詳細設計・制作、システム開発・テスト(約2〜3ヶ月) |
| 5ヶ月目 | 提供開始:コンテンツをリリースし、ユーザーへの提供を開始(効果検証を含む) |
全体を通して、目的設定から企画・開発・提供まで段階的に進めていく流れとなります。
導入の目的を整理する
ゲームコンテンツ導入の最初のステップとして、「導入の目的」を明確に整理しておくことが重要です。何を達成したいのか(新規顧客の獲得、リピート率向上、学習効果の向上など)を社内で共有しておくことで、この後の企画提案が的確なものになりやすくなります。
目的が曖昧なままだと、提供されるゲーム内容が狙いから外れてしまう可能性があるでしょう。
逆に目標がはっきりしていれば、制作側もゴールに沿ったアイデアを提案しやすくなり、効果的なコンテンツ開発につながります。導入前に目的を整理しておくと、プロジェクト全体の方向性が定まり、成功の確率を高められるでしょう。
また、目的に応じて想定される対象ユーザー層や評価指標(KPI)も整理しておくと、より適切な企画提案につながります。
企画提案を受ける
目的が定まったら、次はゲームコンテンツの企画提案を受ける段階に進みます。
ここでは、制作会社との打ち合わせ・ヒアリングが重要です。担当者に自社の課題や狙い、ターゲット層について詳しく伝えることで、提案内容の精度が高まります。
ヒアリングをもとに制作側は最適なゲーム企画を立案しますが、BALANCeではお客様との綿密な打ち合わせを経て、目的達成に沿ったゲームコンテンツの企画を提案しています。
コミュニケーションを密に取り、疑問点を解消しながら進めることで、双方で完成イメージを共有しやすくなるでしょう。その結果、提案されたコンテンツはニーズに合ったものとなり、導入後の効果最大化が期待できるのです。
ゲームコンテンツを実装する
企画が承認されたら、次はいよいよゲームコンテンツの実装フェーズに入ります。ここでは、実際にゲームの内容を形にしていく作業です。
ゲームデザインの詳細設定、イラストやアニメーションなどコンテンツ素材の制作、システムの開発、動作テストまでがこの段階に含まれます。
一連の制作工程には一般的に約1~3ヶ月程度の期間を要します。もちろんコンテンツの規模や複雑さによって変動しますが、十分な時間を確保して品質の担保が重要です。
実装期間中は、必要に応じて途中経過の共有や調整を行いながら進め、企画意図から逸れないようにします。このフェーズを経て、ゲームコンテンツは実際にユーザーに提供できる完成形となります。
サービスの提供を行う
コンテンツが完成したら、いよいよユーザーへの提供開始です。Webサイトやアプリ上でゲームコンテンツを公開し、ターゲットとなる顧客やユーザーが実際に利用できる状態にします。
サービス提供開始後は、コンテンツの稼働状況やユーザーの反応を綿密にモニタリングする必要があるでしょう。どれだけのユーザーが参加したか、狙った行動が見られたかなど、データを収集して効果検証を行います。
導入当初の目的に照らし合わせて成果を評価し、良かった点や課題を洗い出しましょう。得られたデータをもとに、今後の施策改善に活かすことで、次回以降のゲームコンテンツ活用をより効果的なものにできます。
提供後の振り返りまで含めてが、ゲームコンテンツ導入の一連の流れとなります。
ゲームコンテンツの活用事例
スタンプラリーやミニゲームなど様々な種類のゲームコンテンツは、顧客の興味を引き出し、参加意欲を高める効果があります。
ここからは、ゲームコンテンツを活用した事例とその成果を紹介します。
イオン株式会社 / イオンモール中国 施設内回遊デジタルスタンプラリー
イオンモール中国では、来客数に対して各テナントの売上が伸び悩む課題があり、館内の回遊率と滞在時間を高める施策が求められていました。
そのため、施設内を巡るデジタルスタンプラリーを導入し、顧客の購買意欲向上と売上増加を図りました。木を育てるゲーム形式のスタンプラリーを実施し、来場者が各店舗を回るたびにスタンプを集めて仮想の木を成長させる仕組みにしています。
ゲストはゲーム感覚で館内を周遊でき、楽しみながら「ついで買い」(予定になかった追加購入)の誘発や滞在時間の延長につながりました。その結果、平均購買単価の向上など売上アップに貢献し、商業施設内での顧客エンゲージメント強化にも成果を上げました。
さらに、イオンでは人気アニメとコラボしたスタンプラリーも積極的に開催しており、ゲームコンテンツによる回遊促進の効果の高さが伺えます。イオンモール中国は、ゲーム性を取り入れた施策がデジタルとリアルの顧客体験をつなぎ、実際の売上向上につながった事例です。
DENSO / PRゲームコンテンツ
自動車部品大手のDENSOは、自社技術を楽しくPRするためのドライブゲーム「DENSO QR CODE MAZE」を制作しました。電力事業の認知向上や高度な技術力の訴求を目的に企画された対戦型ブラウザゲームで、街全体がQRコードの形になっている迷路を車で走行します。
プレイヤーは制限時間内にゴールを目指しながら街でエネルギーをシェアします。道中に同社の技術を想起させるアイテムや看板が登場するため、遊びながら事業内容への理解を深められる仕掛けです。
誰もが気軽に参加できるゲーム形式にすると、同社の先進技術や事業を効果的にアピールできました。
さらに、勝者に称号が与えられる対戦要素により、ゲーム結果のSNSシェアが促進され、メディアにも多数取り上げられるなど、大きなPR効果を生みました。
株式会社イエローハット / PRゲームコンテンツ
カー用品チェーンの株式会社イエローハットは、交通安全の啓蒙を目的としたキャンペーンサイトにゲームコンテンツを導入しました。ドライバーが危険を予測しながら運転する「かもしれない運転」の大切さを伝えるため、車を操作して障害物を避ける体験型のゲームを制作し、サイト上で遊べるようにしています。
ゲームには同社の公式キャラクターが登場し、親しみやすいグラフィックで楽しみながら交通安全を学べる仕掛けです。さらに、ゲーム画面をプリントしたオリジナルTシャツが当たるX(Twitter)でのフォロー&リポストキャンペーンも同時に実施し、SNS上での話題拡散を図りました。
その結果、ユーザーは実体験を通して「かもしれない運転」の重要性を理解でき、キャンペーンは1,000万を超えるインプレッション(閲覧数)を獲得するなど大きな反響を得ました。
ゲームによる教育とSNS施策を組み合わせることで、社会貢献と企業PRの双方で成果を上げた事例です。
株式会社BAKE / 夏キャンペーン
菓子ブランド「PRESS BUTTER SAND」を展開する株式会社BAKEでは、夏季キャンペーンとしてパズルゲームを活用した販促施策を実施しました。例年夏に売上が落ち込む傾向があるため、ゲームを通して顧客を楽しませながら集客と販売促進につなげることが目的でした。
制作した「BUTTERなサマーゲーム」は、同社商品の材料やお菓子同士をくっつけてプレスバターサンドを完成させる内容で、得点を競うパズルゲームです。ゲームはキャンペーンサイト上で公開され、プレイすると会計時に使える割引クーポンが取得できる仕組みにしました。
さらに、ゲーム結果をX(Twitter)に投稿すると景品が当たるSNSキャンペーンも同時開催し、ユーザーが結果をシェアすると口コミ拡散を促進しています。その結果、ゲームは1万回以上プレイされ、クーポンは1.7万回以上表示されました。
また、キャンペーン告知のX投稿は2.6万インプレッションを記録し、多くのユーザーにブランド認知を広げる大きな反響が得られています。ゲームによる商品理解促進とクーポン施策、SNS拡散を組み合わせた本キャンペーンは、夏場の売上低下を防ぐうえで大きな成果を上げました。
特殊法人 / デジタルスタンプラリー

全国に30ヶ所以上の施設を運営するある特殊法人では、デジタルスタンプラリーを活用して各地の施設への誘客を図りました。全国の複数施設を巡ってもらうため、オフィシャルキャラクターを使った人気投票と連動したデジタルスタンプラリー企画を実施した事例です。
BALANCeがスタンプラリーのシステム提供からキャンペーン企画・デザイン・開発まで一貫して担当し、参加者はスマホを片手に各地の施設を訪れスタンプを集めながら、キャラクター人気投票にも参加できる仕組みを構築しました。
デジタル上での投票と実際の現地訪問を組み合わせると、オンラインとオフラインの両面で顧客との接点を増やすことに成功しています。離れた地域の施設への来訪促進につながり、ゲーム性を活かした効果的な集客施策となりました。
このようなO2O(Online to Offline)の取り組みにより、デジタルとリアル双方で利用者の体験価値を高めています。
ゲームコンテンツの制作ならBALANCeにお任せください
デジタルスタンプラリーやオリジナルゲームなどのゲーミフィケーション施策は、顧客の興味を喚起し、行動を促進する強力な手法です。本記事で紹介した事例のように、商業施設での回遊率向上から企業PR、交通安全啓発、販売促進、地域誘客まで、ゲームコンテンツは様々な分野で高い成果を上げています。
ユーザーが楽しみながら参加できるため、従来の手法では得られにくかった高いエンゲージメントや話題拡散効果を生み出せる点も大きな特徴です。
ゲームコンテンツ制作の豊富な実績を持つBALANCeなら、ゲーミフィケーション施策の企画から開発・運用までワンストップで支援可能です。
これまで様々な業界・目的でゲームコンテンツを手掛けた経験とノウハウを活かし、お客様の課題に合わせて最適な施策をご提案いたします。
ユーザーに響く魅力的なコンテンツでプロモーションの成功を後押しするため、ゲームを活用したキャンペーン制作をお考えの際はぜひお気軽にご相談ください。